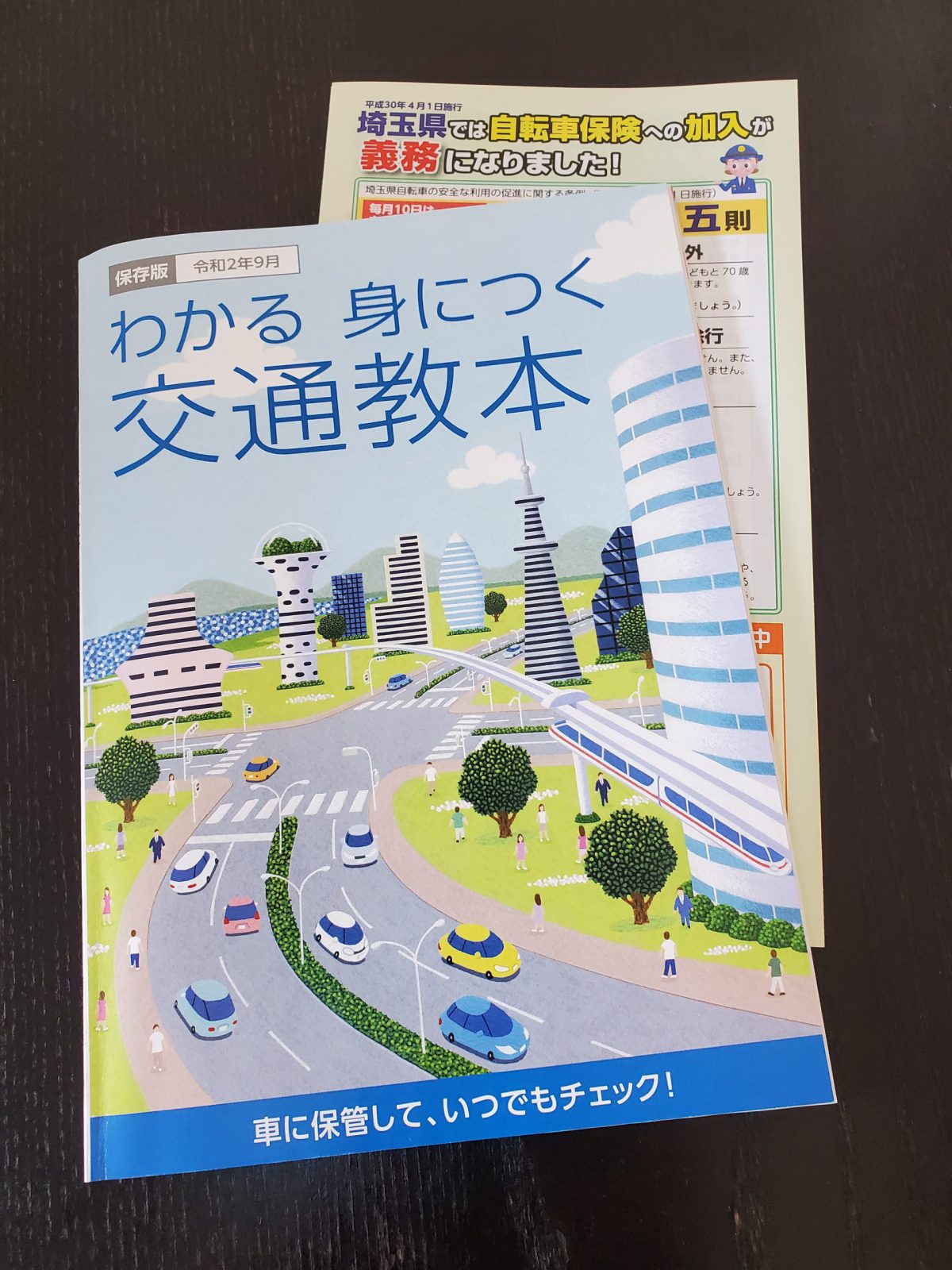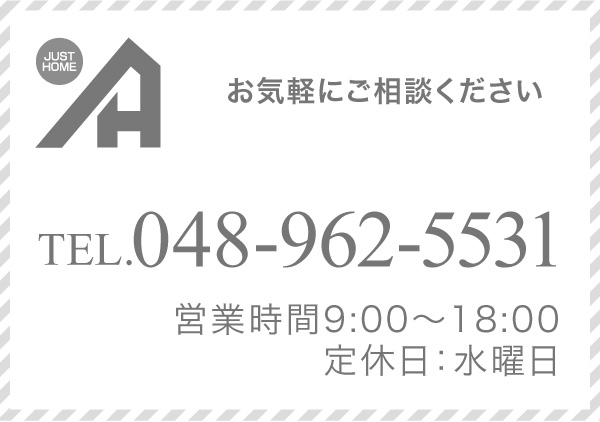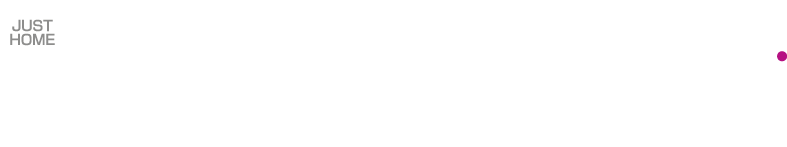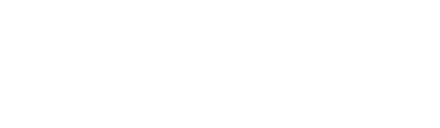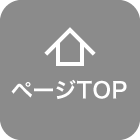昨日、朝テレビを観ていたら
柏のあけぼの山農業公園のチューリップが
放映されたので、天気も良く暖かかったので、
午後から見に行って来ました。
テレビの力は、大きく大勢の人で
とても賑わっていました。
あけぼの山農業公園は、
『遊んで学べる花の里体感ファーマーズパーク』が
キャッチフレーズになっていて、
加工実習館やバーベキューガーデンなどの農業公園ゾーンと、
市民農園や、柏市のシンボルともいえる”風車”がある
体験農園ゾーンがありました。
花畑では、チューリップの他にも、季節よって
ヒマワリやコスモスなどが咲き楽しめそうです。
また、夏に向日葵を見に行こうと思います。
あと隣接するあけぼの山公園は、
桜の名所として親しまれているほか、
茶室「柏泉亭」がある日本庭園や、
ハナショウブが咲く水生植物園がありました。
入園と駐車場も無料になっていますので
機会がありましたら、是非一度
皆さんも行ってみてください。