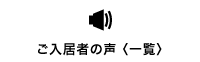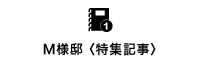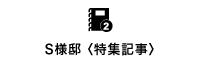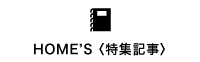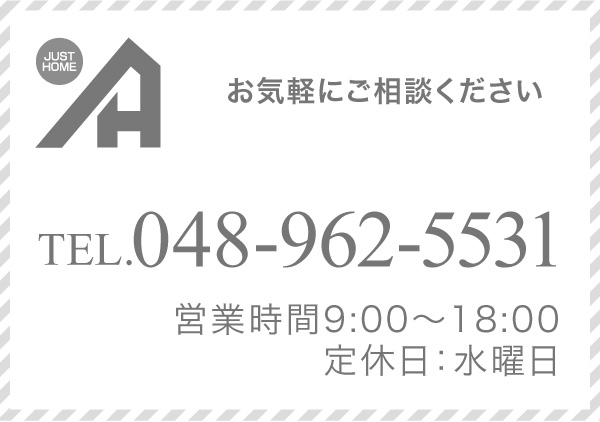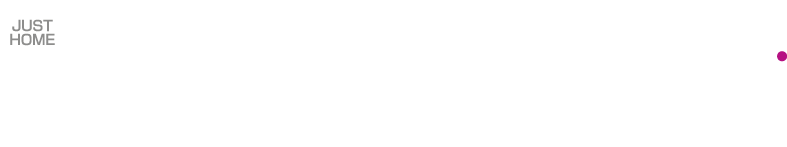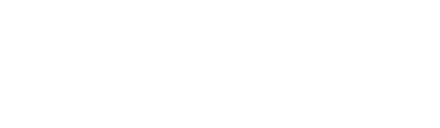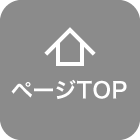入居者の声
リフォーム体験記:やるなら徹底的に、壁紙で魅せるオンリーワンのSumai
2025.10.18
築25年のお宅のリフォームを行いました。キッチンとお風呂を新しいものに交換し、それにあわせて、壁紙を大胆に張り替えました。毎日生活をする家は、毎日帰りたくなる家であって欲しいものです。長年の夢を叶えたご夫婦にお話をうかがいました。

Q: O様邸は築25年と伺いました。今回リフォームした場所はどこでしたか。
奥さま:お風呂場、キッチン、リビング、階段、あと2階の廊下です。
会田社長(以下JH):壁紙クロスはLDKと2階の廊下まで。交換した設備はキッチンとお風呂。そしてそれに合わせてソファー、テーブル、テレビボードなどの家具を一通り変えましたね。カーテンも変えましたか?
奥さま:変えました。あと、階段のところのロールスクリーン。
Q:まず印象的な壁紙についてお伺いします。以前はどんな壁紙だったのですか?
奥さま:白です。白一色。
JH:新築の時に、クロスを選んでいるんですけど、わざわざ柄ものを使うっていう感覚はなかったですよね。
奥さま:当時はないですよね。発想もなかった。若かったな。定番の色というか、無難な白色でした。でも部屋が広いんで、食べる空間とリビングの休む空間とをちょっと分けたいと思って、色を3色使いました。やるんだったら、もう全部やっちゃおうかなと。
JH:ゾーニングをしたわけですね。
奥さま:色を分けないとただの白い空間になっちゃって、めりはりがなくなっちゃうので、分けたんです。

Q:黄色は目を引きますね。
JH:黄色はもう奥さまのテーマカラーですね。
奥さま:大好きな色です。
Q:とてもいいと思います。濃い色は好きです。
JH:思ったよりジョイントも目立たなかった。
奥さま:こういう広い空間の一面は、薄い色より濃い色の方がいいですよね。
JH:ええ。薄い色はより薄くなっちゃうんですよね。見本でちょうどいいぐらいだと実際には薄くなってしまうことがよくあります。
奥さま:見本でちょっと濃いかなって思うぐらいがちょうどいいのかな。
JH:その通りです。

奥さま:柄がちょっとあるぐらいだとインパクトがないので、ちょっときついぐらいの柄の方が目立ってインパクトがあるかなと思ったんです。
JH:その柄もすごくいいと思います。
奥さま:黄色に黄色を使ってるから。
JH:ひきたて合ってるんですよね。こっちの黄色が結構濃いんだけれども、こっちの黄色が薄くて、何かいいんですよ。
Q:この柄は、すぐ見つかったんですか?
奥さま:サンゲツさんの見本帳で探しました。
JH:2色あったんですよね。この柄の色違いが。
奥さま:でも黄色が入っていたので、もうすぐこれに。
JH:この柄だと、インターホンや給湯器のリモコンが目立たないんですよね。悪目立ちしない。で、見ているだけで楽しい。仕上がりを良くするために下地のボードを変えて正解でした。

Q:この1列がいいですね。
奥さま:最高じゃないですか?
JH:最高ですよね。
Q:これは奥さまのセレクトですか?
奥さま:そう、パンフレットを見て、どうしてもこの柄を使いたくて。
JH:白の帯で、こう分けるというのは斬新ですよね。非常に複雑な張りわけで、判断に迷うところを的確に処理しています。立体的な思考ができないと思い付かないと思う。

Q:キッチンの改修ではハプニングがあったと聞きましたが?
JH:キッチンの下がり壁を撤去し、カウンターも新しいものに交換しようとしていたのですが、私が採寸を間違えて、3センチ短いカウンターが届いてしまったんです。絶対間違えちゃいけない場面で、間違えちゃいけないミスをしてしまって・・・。しかもそれが分かったのが私が参加していたマラソン大会のスタート直前で、大工からの「どうしても収まらない」という電話でした。材は取り直しになり、結局10日ほど工事を伸ばしてしまいました。
Q:新しいシステムキッチン、今までと違う機能は何かあるんですか?
JH:食洗機をつけなかったんです。
奥さま:食洗機はいらなかったんです。自分の手で洗わないと気が済まない。まずそれがなくなって良かったなと思う。収納は今は引き出しタイプで、すごくいっぱい入るっていうことと、前はしゃがんで奥のものを引っ張り出したり重ねたりしていましたがそれがとても楽になった。収納の仕方によって物がいっぱい入るようになりました。

JH:キッチンの収納は20年ぐらい前からトビラ型から引き出し型が主流になっていますが、引き出しの方が便利ですよね。
奥さま:あと吊り戸棚も取って正解。自分がそんなに背が大きくないから、いつもつり戸棚使う時旦那に頼むか、椅子を持っていくかしないといけなかった。あと一番上の棚は届かないので使わないものをずっと上に置いておくだけだったので、スペースがもったいなかった。
JH:吊り戸棚があると要らないものがそこに入っちゃいますよね。
奥さま:そう、だからなくして正解。要らないもの、もうほとんど捨てちゃいました。あと、ここ。キッチンとカップボードを揃えたのですごく使い勝手が良くなりました。
Q メーカーはどちらですか?
奥さま:タカラスタンダードです。
JH:もともとタカラのキッチンでした。結構キャビネットがしっかりしてたんですよね。15年25年経っていてもガタが来てなかったんです。だからやっぱり今度もタカラにしておけば、30年経ってもガタが来ないだろうと。
奥さま:壊れてないのに取り替えとなりました。 食器棚を買って、その隣にまた違う棚を買って・・・と、もう本当に継ぎ足しみたいなキッチンだった。今回はもう全部揃えたいって言って、同じものを揃えたんです。
Q:気持ちいいですね。
JH:気持ちいいよね。見ていても気持ちいい。でも、使ってても多分気持ちいいと思う。
奥さま:汚したくないです。揚げ物とかはだめ。主人には食べたければ実家に行ってくださいって言っています。
JH:・・・・
奥さま:天ぷらとかあげて汚したくないんです。

Q:ご家族以外で誰か、見てびっくりされた例とかありますか。お友達とか。
JH:ご主人のお母様がいらっしゃったとか。
奥さま:見るなり、あらーって。 この黄色はインパクトあったんじゃないですか? 目が痛いっていう人もいます。
JH:クロスの張り替えって結構大変です。でも大変な思いをするんだからこそ、思いっきりやっちゃった方が達成感ありますよね。当たり障りないことをやるよりは。
Q:アクセントクロスの使い方は、日本人は苦手ですね。せっかくのアクセントクロスなのに地味なものを選びがちです。派手な柄はトイレの壁とか、あまり人の目に触れないところに使いがちです。
JH:ウォークインクローゼットの中とか、あと物入れの中ね。小さい物入れの中だけ柄物にするとか。 自分の好きな色なんだから大胆に使っちゃえばいいのにと思うんですけどね。普通は奥さまほどの領域に達しないと遠慮しちゃうんですね。
奥さま:もったいない。 好きな空間に使えばいいのに。

JH:多分派手でも大丈夫なんですよね。その人は好きなんだから。それこそリビングとかでドーンで使っちゃっていいんだと思う。キッチンのこういうクロスの使い方いいですよね。Oさんは本当にクロスに関してはコーディネーターの域だと思う。
奥さま:とても楽しくて。考えてる間が楽しい。
JH:決断は早かったです。ふたパターンすぐできましたもんね。
Q:カタログを見ていると楽しいですよね。
奥さま:楽しい。
JH:ご主人は最初ちょっと渋い顔をされていましたけど、終わってみたら晴れやかになった。
奥さま:全然、違和感ないもんね。
ご主人:そうだね。
JH:最初はびっくりしました。私は一番最初だけびっくりしましたよ。一番最初、玄関のあのクロスになってから初めて来た時は。
奥さま:そうなんだ 全然違和感ないけど。
JH:もう慣れました。でもあの玄関があったからこそ、リビングが物足りなかったですよね。そう、はっきり言ってただの白で。結構黄ばんでたし。あと昔ながらの天井用のクロスでしたしね。

Q:今度さらにリフォームするとしたらどこでしょう?
奥さま:もう大丈夫じゃないかな。あと真ん中の娘の部屋ですが、それは自分でやらせる。そうすれば全部完了。 あと2階のおトイレが残ってますね。
JH:それぐらいだったら、多分ご主人もクロス張れるんで、何とかなりますね。
奥さま:トイレ直すのは大変そう。できれば収納棚をつけたいと思っています。
JH:いろいろな方法がありますよ。
奥さま:ではちょっと考えてみます。その時が来たらよろしくお願いします。

Q:これからリフォームを考えてる人に心構えをアドバイスしてください。
奥さま:迷ってるんだったらドカンとやっちゃった方がいい。
JH:自分もそう思います。遠慮しちゃって、あとから「もっとやっても良かったなって思うぐらいだったら、やり過ぎたぐらいでいいと思う。
奥さま:そう、やった方がいい。
JH:攻めの姿勢が大事だと思うんですよね。その方が人間、若くいられそうな気がする。人間味っていうか、原動力って言うか、分かりますかね。あんまり守りに入ってるとなんか老け込んじゃうような気がする。
奥さま:あんまりシンプルでもつまんないし、自分が好きなことをその時やった方がいい。そして、自分の家に帰りたくなるような家づくりをした方がいい。
Q:名言ですね。

JH:リフォームはとても大変ですが、一方でとても楽しかったです。
奥さま:職人のみなさん、本当に大変だったと思います。でもとてもよくしていただきました。作業の後の対応がすごく良かった。この黄色いクロスを貼って1日2日経った後に、クロス職人の方が様子を見に来てくれたんです。本当に感謝しています。大工さんも最高でした。
Q:本日は貴重なお話をありがとうございました。次のリフォームの時もまた、よろしくお願いいたします。